久々にパソコンに保存している四国の山なみを見ていたら、、、
保存・紹介しています

四国の山なみ~古典山岳文献/土佐の近代登山史 | Trekking from Kochi
たまたま見つけた『四国の山なみ』ってサイトですが消えてしまう可能性があるので保存・紹介します

サイトの丸ごとダウンロード | Trekking from Kochi
サイトを丸ごと一括で保存する方法
ん!? この話が白髪山の名前の由来じゃないか!!
宮古野白髪神社
樹齢三百年
感想
この話が本当とするならば、白髪山(通称奥白髪)の山名は、近江(滋賀県)の白髭神社からきてる!?
猿云々は昔話的な物(作物を食い荒らされて飢餓に陥った等が元の話)かもしれませんが、森近江が高知に居た、存在したのは本当らしいので白髪山の山名は白髪大明紳が関係しているって言うのは有力だと思う。。。
と
思ったんですが、、、、
白髪神社
土佐郡森村宮古野に郷社白髪神社
元々は奥白髪山冬ノ背に小さな社があったそうです
宮古野の白髪神社

白髪神社 - 【公式】汗見川情報サイト|高知県本山町
精巧な社は昔、宮大工が来て建築を始めた際に子供ができ、社が完成した時にはその子供が小学生になっていたといわれるほど年月をかけて建てられたと伝わっています。また、白髪神社の下の川辺は川遊びで人気のスポットです。
分霊された沢ヶ内にある白髪神社
白髪大明神
故国の白髪山を移して白髪大明紳を勧請したという。
現在、滋賀県に白髪山と言う山名の山は検索では出てきませんでした
白髪大明紳も存在しないと、、、
白髪大明神と言うのは嶺北地域独特の表現なのかもしれません
汗見川の奥なる白髪の老翁に出遭い奇瑞を得てから
ここを読むと白髭ではなく白髪なので白髪大明神になったのか、、、
髭と髪の違いなので地域で伝説・言い伝えが違うのかな、、、
白髭大明神は検索でも出てきます
白髭大明神(猿田彦命)を祭っている滋賀県の白鬚神社
森近江の故国って事で間違いない
猿田彦命
一日森近江は本山郷汗見川の奥なる白髪の老翁に出遭い奇瑞を得てから、附近の者どもはこの白髪の老翁を崇敬し白髪山に参詣する者漸次に数を増加して来たので、森、本山、本川の村人らは右三郷の中央の森の中へ社殿を建立して白髪大明神と称し崇敬祈祀し、その所を宮古野と称したという。
白髪の老翁が猿田彦命なのですが、、、
ただ、森近江が猿田彦命に会ったから白髪神社を作り祀ったとすれば白髭神社から分霊する必要はないんだよなぁ。。。
故国の白髪山を移して白髪大明紳を勧請した。
↑の話しの最初の部分が破綻する。。。
最初は、この話が本当だという説で調べていたんですが、、、
色々疑問がでてくるんです
けど、本当の話しだとしても昔話って奴は表現を変えて伝えていたりするし、全てを事実として捉えると無理がある表現が出てくるだろう、、、と思ったんですが、、、
山名の由来
本山町のHPにある山名の由来は、、、
「白く光る岩」に由来しています。以前は白い岩を意味する白峨の文字を使っていましたが、今の奥工石山に猿田彦神(白髪の老翁)を白峨の山霊と奉ってから「白峨」を「白髪」に改めたといわれています。
つまり、元々『しらが』であって、漢字が変わった理由が猿田彦神を祀りだしてからだと、、、
何故、奥工石山に祀って白峨が白髪になったんだ、、、
白髪山の神様なのに工石山に祠、、、
元々は工石山と白髪山は区別してなかった???
工石山には別名が多い(立川工石山、竜王山)のも、白髪山から独立した後に山名がつけられたからなのか???
もう謎が謎を呼ぶ状態になってます
奥工石山にはゆるぎ岩と言う目立つ、立派な岩があり白髪山の山名の由来(白く光る岩)の岩としか思えません
そのゆるぎ岩には白山神社があります
この白山神社がそうなのか?
白い山って文字からも白髪山との関りが想像できるんですが、白山神社は神様が猿田彦命とは違う別の信仰なんだよなぁ。。。
昔、奥白髪と奥工石は一緒の山とされていた?
白山神社が元々の山名由来だとすると奥白髪山は元々白山と呼ばれていた??
白髪、工石が一緒だったのか、、、それならそれでどうして別々になった、、、工石が竜王と呼ばれるようになったのは、、、猿田彦の話は伝承された話なのか、それすら完全な作り話で森近江(統治者)に箔をつける為だったのか、、、奥白髪には山賊岩と呼ばれる場所がある、、、山賊退治なんかも伝説があるのか、、、、、、、、、、、、、、、、、、
あぁぁぁあああぁぁぁぁっあ!!
もう無理!!
調べるのを諦めた理由
本山町としては、森近江が猿田彦命を祀って白髪神社~白髪山って話を推しているんですが、、、
由来、伝説としては良い・使いやすい話ですよね
ただ、個人的に色々矛盾と言うか謎が多すぎて納得はできない
Google先生に聞いていると全く違う話が出てきました
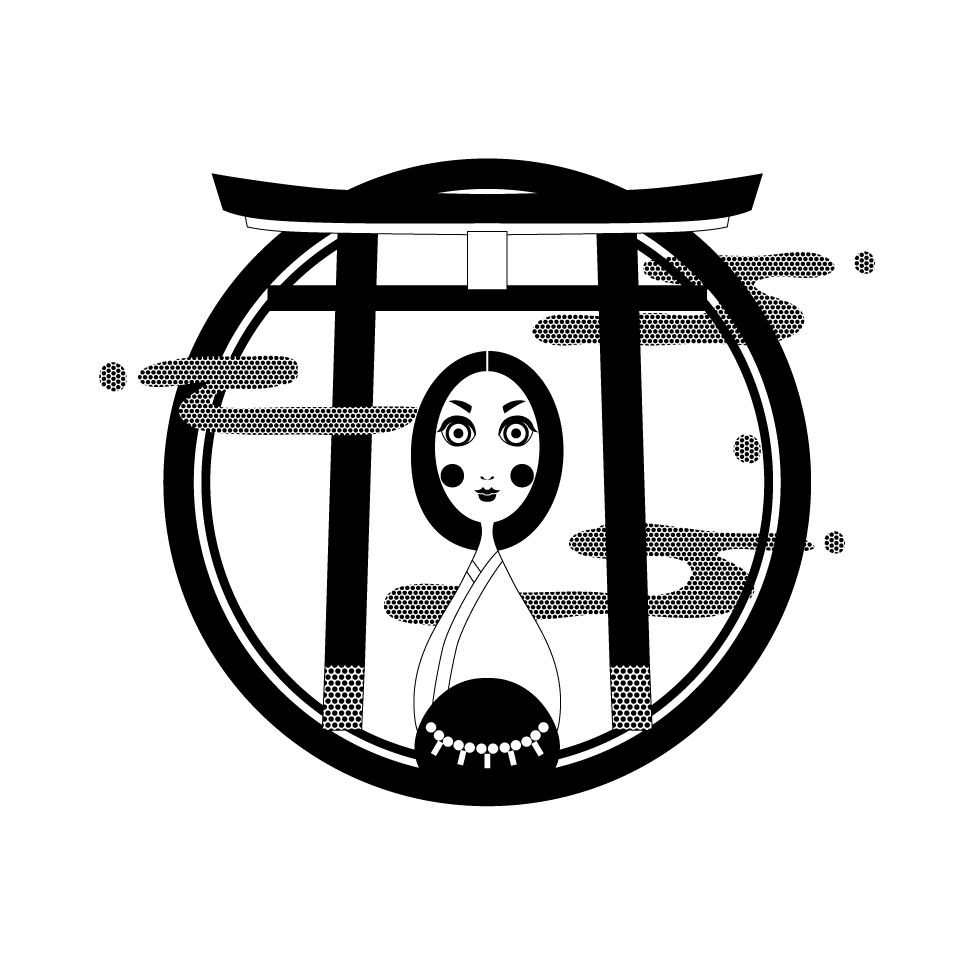
白髪神社 | とさちょうものがたり
白髪神社は土佐町宮古野地区にあり、周りが田んぼの中、その場所だけ木に囲まれるようにして静かに建っています。 その白髪神社のお話です。 白髪神社信仰は、高知県下でも吉野川上流にのみみられるものである。 土佐町宮古野、大川村大藪、本川村(現在いの町)桑瀬、いの町長沢、いの町越裏門、いの町寺川、本山町沢柿内で 「産土神」として鎮座している。 越裏門、寺川あたりでは「本川女に森男」という俚諺がある。 これは本川郷((かつて本川村から東隣の大川村を含む一帯を本川郷と呼んだ))の美女、森郷((現在の土佐町))の美男子という意である。 本川郷にまだ白髪神社を勧請((神仏の分霊を他の場所に移しまつること))していないころの話である。 土佐町宮古野白髪神社の祭りには、老若男女の氏子たちが本川郷からもはるばる何時間も歩いて出掛けていた。 ところが本川女は祭りの準備やら、籠り人の食事の煮炊きなどばかりさせられ、 森の男たちは上座に威儀を正していい格好で座ってばかりいる。 そこで本川女も「時にはわしらも上座に座らせよ」と言うと、 森男は「そんな伊賀ばき(昔の田舎びた服装)の者を座らせるわけにはいかぬ」という。 さすがの本川美女もこれには腹を立て、 竃(かまど)の石を取って「氏神様もついてごさっしゃれ」と言って越裏門、寺川に帰ってしまった。 その竃の石を祀り始めたのがこのあたりの白髪神社であるという。 ところが持ってきた石に、森の白髪神社の御神霊が本当に憑いてきていて、 森の方では神様がお留守になったと大騒ぎになった。 そこで森男から本川女に詫び状が入って、本川から神霊がお帰りになったという。 森から石を奪ってきた日が戌亥(いぬい)(=乾(いぬい))であったから、越裏門は十一月戌、寺川は亥の日を祭日としたとか、 白髪様の祭りを乾祭りというのだと言い伝えて、戌亥信仰((戌亥は北西の方位を指す。怨霊や魑魅魍魎などの災いが出入りする方角であるとして忌むべき方角としている。この方位を鎮めると、家運が永久に栄え、子孫が繁昌するとされ、神棚や神社を設けて信仰されていた))が見られる。 土佐町史839p
↑の記事にコメントがあったので見てみたら、、、
もうこれ以上調べる気にならなくなりました
余程の専門家、地元の生き字引・言い伝えを受け継いでいる方
そんな方々が集まって話すれば着地点が見えて来るかも、、、
白髪信仰は嶺北固有の信仰とも言える、白髪村(現宮古野)、長徳寺(現在の若一王子社付近)の鎮守であった「白我社」、、、、、、、、、、、、
もう解明できないと思う
勝手な想像
嶺北山岳信仰
山岳信仰だと仮定して嶺北山岳信仰と勝手に命名します
日本全国を見て(Googleマップ調べ)白髪神社って高知にしかないんですよ
本山には汗身川沿いに白髪神社があります
山から分霊で里に降りてきたってのが場所からも容易に想像できます
森近江の話は作り話でも嶺北固有の信仰があったのは間違いないかなと
山岳信仰とするのが一番しっくりきます
白髪神社は本川、いの町、物部にあります
嶺北山岳信仰が伝わって分霊した、、、って話だと場所的にもしっくりくる
白髪神社が猿田彦命を祀っているのは、、、
森近江との関りが考えられるので、白髪と名前が変わったのは森近江が高知に来てからの話だって言うのは正解
森近江(統治者)に箔をつける為に元々あった嶺北山岳信仰を森近江由来に変更した
嶺北山岳信仰も猿田彦命を祀っていたと仮定したら全ての話が納得はできる
森近江の話が作り話だとしても神様は変わっていないんだから
白髪、白髭ではなく髪なのは、、、嶺北山岳信仰に配慮したからのか、、、
白髭にすると近江(滋賀)とは関係ないんじゃ!!と猛反発食らうから白髪にして濁したのか、、、
また謎が謎を呼びます
もう想像も限界と言うかキリがない
誰か歴史調べている人がなぞ解明してくれないかな。。。
白髪山(香美市)との関係は?
高知にある、もうひとつの白髪山
山名が全く一緒なんですが、こちらの山名の由来をGoogle先生に聞いても出てきません
冬季は真っ白い冠雪の頂で山名の由来もそのあたりかもしれない
見つかったのはコレだけ
白髪(本山)の山名の由来は結局解らなかったんですが白髪山と言う山名になっているのは間違いないわけで、白髪神社が分霊をして幾つもあるのも間違いない事実
嶺北地域になにか信仰があったのは間違いないのではと思う
その白髪山と漢字も全く一緒の山名で白髪神社も香美市物部町にある
本山から分霊された神社なんだろうか?
同じ山名、神社がある、、、何も関係ないとは思えない
ただ白髪山信仰だとすると白髪山がふたつあるのはおかしな事になる
こちらの白髪山の山名由来が不明なのも謎が謎を呼びますよねぇ。。。
更に、、、
高知には工石山がふたつあり、白髪山と一緒で工石山、奥工石山と呼ばれている
白髪山、工石山が両方あるのが本山、しかも隣り合わせの山
奥と呼ばれているけどこちらが元々の工石山、白髪山?
工石山には妙体岩と言う奥工石山のゆるぎ岩と同じような目立つデカい岩がある、、、
本山の工石山は竜王山と言う別名がある、峠の名前は竜王峠、、、
駄目だ、もう考える・想像するのをやめないと絶対にキリがない
だって答えがない、立証できるものはないんだから
なにもかも謎で終わってしまいました
最後まで見てくださって、本当に有難う御座います m(__)m







コメントを投稿