四国の山なみ保存計画第十二弾
古典山岳文献 四国の山山 の中から 白髪山(奥白髪山)を紹介します
第一弾はコチラ

四国の山なみ~古典山岳文献/土佐の近代登山史 | Trekking from Kochi
たまたま見つけた『四国の山なみ』ってサイトですが消えてしまう可能性があるので保存・紹介します
古典山岳文献
四国の山山 ~ 白髪山
長岡郡本山町から大橋を渡り、野中兼山ゆかりの地、帰全山を経て北へ十四㌔、約三時間で頂上に達する。
標高一四七〇㍍、国境尾根の一支峰である。
途中は指導標も割合に整備されているが、欲をいえばもう一、二カ所設置してあったらと思う。
急な登りも殆どない一本道なので岐路の心配もまずなく、高知を早朝に出発すれば日帰りもできるが、前日の午後にでも出発して吉野川の川原でキャンプをすればゆっくりした山行を楽しむことができよう。
初夏のシャクナゲ、秋の紅葉はさらに目を楽しませてくれる。
奥工石山から
山脇哲臣氏撮影
頂上からは土佐平野を一望の下に収め、遠く太平洋まで望むことができる。
頂上付近のシャクナゲとヒノキは美しい。
とくに頂上南面の白骨化したヒノキの眺めがよい。
これは大正の御大典記念として、保護林に指定されている。
昔からこの山はヒノキのほか、モミ、ツガの良材を産することで知られており、とくにヒノキは土佐名物の一つとして、長曽我部元親から豊臣秀吉へ献上されたという記録もある。
徳川時代に大阪長堀の土佐材木問屋のあった町名を、白髪町といったのを見ると、この山のヒノキ材がかなり積み出されていたのではなかろうか。
梶ガ森ほど知られてもいないので登る人も少ないようであるが、それだけに静かな山行を楽しみたい人々のために、推奨したい山の一つである。
(「四国山脈」より・昭和三十四年、高知山岳会 坂口 忠智)
暗夜の奥白髪山行
昭和三十八年(一九六三年)正月元日 寒波襲来の報あり。
風強く寒し(補遺:当時の気象台の記録を調べてみると、高知市で最高気温九・九度、最低気温が氷点下一・五度、最大風速六㍍、本山町の記録なし)。
一行は、印刷会社の社長(五〇歳位)、職場の先輩(四五歳)、筆者(三〇歳)の三人。
計画は、本山町瓜生野から山頂を目指し、帰全山に下るコースである(下図参照)。
「この山は、磁鉄鉱があって磁石が狂う。一度迷いこむと、二度と出られない」と、聞いていたので、ふと、思いついて懐中電灯を携帯していったのがよかった。
五時五分起床。
自転車で高知駅に向かう。
まだ夜は明けていない。
六時二十五分発の高松行き普通列車に先輩と乗り込む。
大杉駅まで百十円。
後免駅で社長が乗車しないので、知り合いの駅長に「時間の都合で先に行く。悪しからず」の伝言を依頼(補遺:昔は、何事もおおらか)。
客室は、金毘羅さん初詣の参拝者と思われる乗客で賑やか。
大杉駅着、七時四十六分。
直ちにバスに乗り、冬の瀬線に乗り換えるため、本山で下車。
八時五十分発車、九時五分、田井着。
五分間の停車時間に、煙草を吹かしていると、だしぬけに社長が現れたので仰天。
後発のバスの運転手を急がして、追いついたという。
三人、肩を叩き合って、大いに笑う。
「つれない人達だ」と社長が嫌みをいう。
九時五十五分、瓜生野(三七〇㍍)着。雑貨屋で、パン、味噌等を買い、登山コースを聞く。
地図に記載されているコースは、廃道となっているとのことで、詳しく教えてもらう。
歩行ルート図
詳細な地図は上記画像をクリックして下さい
※クリックした時の地図
十時二十分、出発。
迷いやすい岐路が多いと教えられたとおり、いきなり、道を間違えた。
後ろの声に振り向くと、大人と子供が数人、盛んに、手まねで本道を教えてくれる。
親切な人達である。
了解の手を振る。
十一時三十五分、白髪山西側の口白髪谷に出遭う(補遺:六五〇㍍付近か)。
ここで食事。
雪がチラチラして、風が強く、とても寒い。
飯盒飯を炊き、味噌汁に餅を入れて正月を祝う。
十二時三十五分、谷を左に見ながら進む。
間違いやすいので注意、谷を渡ってはいけない。
白髪の山容は見えない。
登るにしたがい、道の雪が次第に目に付きはじめる。
熊笹が多くなる。
多分、尾根伝いと思われるこのコースには、熊笹、桧、石楠花の古木が多い。
桧は、母木が枯死、五十年位を経た新生木に交代している。
一一〇〇㍍位か? 積雪五㌢。
次第に降雪が多くなるが、風はなくなった。
三十分歩き、五分休むというペースで進む。
三叉路(補遺:一二〇七㍍)になかなか着かない。
地図が間違っているのか、道を迷ったのではないかと思うほど、遠く感じる
(補遺:これは、多分、そこから見る山の姿によって目標が指呼のように感じられにもかかわらず、実は、似たような地形によって錯覚してしまうためではないか、と思う。今でも、その時の強い印象があり、これが再度の登山を敬遠する一つの理由にもなった)。
白髪山のいたるところにある桧の白骨林
十五時、ようやく三叉路にたどり着く。
登りはじめて、すでに五時間を経過している。
ここに荷物を置き、十五時五分、頂上に向かう。
周囲も空も薄暗い。
石の多い雪道を、足を滑らさないように注意して登る。
この付近から山頂までは石楠花の群落であり、ただただ驚嘆する。
社長は、激しくなる降雪と次第に薄暗くなる不気味な雰囲気に怖れを抱きはじめたのか、登頂を断念しよう、と迫りだした。
なんとか宥めながら、ただひたすら進む。
先輩はどうかというと、元来、腹の座った人で、簡単には弱音を吐かない。
小生は若いだけで、怖さ知らずの若輩者。
胸中にそれぞれ不安はあろうが、ここで引き下がるわけにはいかない。
思いは、多分、皆同じだろう。
十五時二十五分、風穴に行きあう。
穴には棚のような台があり(蚕種貯蔵の目的?)、宿泊もできるようになっているようだ。
「なにかあれば、ここで泊れる」とひそかに思う。
現在の風穴の中
建造物は朽ちるにまかせられている
石楠花の林を登りつめると、遂に山頂(一四七〇㍍)。
十五時四十五分、立つ。登りはじめて、五時間二十五分。
降雪のため視界はきかず、風でいじけた五葉松や樅、桧の白骨林に雪が付着し、一面の銀世界。
沛然とした四囲をただ呆として眺めるのみ。
三本の木を組み合わせた簡素な三角点がある。とても寒い。
現在の白髪山三等三角点
十六時、心を残して、下山開始。十六時四十分、三叉路に着き、あり合わせの腹ごしらえ。
そこへ四人の猟師と二匹の犬が来る。
猪を追っているとのこと。
なにやら自信ありげで、不敵な面構えに畏敬の念。
こちらも、なんとなく勇気づく。
十七時十五分、出発。もうかなり暗くなっている。
社長がまた何やらボヤク。
三叉路からは往路をとらず、南下して、まずは帰全山を目指す。
それぞれ杖を作り、小生が三人の真ん中を歩き、懐中電灯で、もっぱら前方を照らしながら、慎重に足を運ぶ。
やがて、あやめも分からぬ暗闇の歩きになった。
ふと、電球が切れたらどうなるのかと思う。
六九〇㍍付近の分岐に、次のような道標があった。
「上れば山頂、下れば日浦をへて上関に至る」
右にも別の道があり、これが帰全山への道だったが、誤った。
しかし致命的ではない。
十九時三十分、日浦。二十時四十分、上奈路。歩行時間は延べ十時間二十分。
ここで、タクシーを呼び、大杉駅に二十一時ごろ着く(七一〇円)。
二十二時四十一分、大杉発高知行き普通列車で、二十三時四十八分、高知駅着。
「一泊すれば楽な山だが、日帰りは無理だ。もうあなたとは山へ行かない」 と社長が苦笑しながら、吐き出すように言った。
白髪山山頂。眼前にきびす山、その麓が帰全山
登山口である瓜生野の標高は三六〇㍍だから、登攀の標高差は一一一〇㍍という厳しさである。
因みに、面河から石鎚山のそれは一二六〇㍍、葛籠から剣山のそれは一三一〇㍍だから、これらに匹敵するのである。
昭和三十四年に発行された「四国山脈」に以下の記述があります。
「野中兼山ゆかり地、帰全山を経て北へ十四㌔、約四時間で頂上に達する。急な登りもほとんどない一本道なので岐路の心配もまずなく、高知を早朝に出発すれば日帰りもできるが、前日の午後にでも出発して吉野川の川原にキャンプすればゆっくりした山行きを楽しむことができよう、云々」
全く、その通りと思います。
私どもは、降りでしたが、同じような消費時間であり、夜の歩きというハンディを考えると、われらの足も満更でもなかったと思われます。
今なら高知から大豊IC、本山東大橋を渡り、上関、新頃を経由して、千五十六㍍地点で車を置き、後は、徒歩で一時間余りと、少し味気ないものになりました。
なお、社長と先輩は故人になられております。
注、この紀行文は、「山登の部屋」(リンク集参照)にも掲載されています。写真はほとんど「やまとさん」が添付してくれました。なぜか、当時の写真が一枚も残っていないのです。 (平成十五年記)
白髪山の怪物
弘化三年の頃、本山郷汗見川村に松井道順という医者があった。
近郷まで聞えた名医でよく病気の根源をたしかめ如何なる難病も松井にかかれば治らぬこともないとの評判であった。
道順が六十になったとき不老長寿の霊薬「貴精香」を求めんと思ったが
「この霊薬は民間にあるものでなく或は深山幽谷を探ればあらん」
との話を聞き、只一人白髪山に分け入った。
山又山を尋ねたが一向「貴精香」がなかったので
さらに人類未踏の深山に入りここで滞留すること三日、持参の食糧も乏しくなったのでもうそろそろ下山しようと用意中、
杉桧の密林中がざわざわと揺ぎその中から現われたのは丈八尺ばかり、
頭のまん中に一本の黄色な大角をはやし顔面は朱の様に赤く眼は星の様にキラメキ渡る怪物が近寄った、
道順は驚いて地へ伏した。
「コリャ道順!顔をあげろ、ぶるぶるふるえ驚くには及ばん、わしは全世界人の死人のかたまりじゃ!死人の霊魂がかたまったのがわしじゃ…。
わしは生き残っている人間に病を授け一日も早くわしの国へ呼び寄せることがわしの役目じや!
わしの国には閻魔大王もなければ針の山もない、わしの国は異人の霊魂と日本人の霊魂とが入り乱れている。
しかしお前は名医でわしの国へ来る人々の命を長くしている、
わしから考えると甚だ不都合でとり殺してやり度い位憎いが、お前が霊草、霊木を基にして薬をこしらえ病人を直す心根だけは感服にあたいする、
すべて病の原因と治療の方法はわしが纏めてこの一巻にある、
只今これをお前に授けるによってよく吟味せよ……」
そういって両手をあげ空に向って三四度招く格好をしてから更らに語を次ぎ、
「昔から汝は長生をした人の話を聞いているだろう、
支那では東方朔が三万八千年、西洋では「ノア」の九百五十年、「アダム」の九百三十年、
日本では浦島太郎の三千年、武内宿禰の三百年、神武天皇の百二十歳、仁徳天皇の百四十歳、大石良雄の妹清舟尼が百四十四歳、
また三河国宝飯郡の万兵衛が二百四十三歳、土佐では比島竜乗院の日讃上人が百六十四歳など長生きをしたものじゃが何れもわしの国へ来ている、
秦の始皇帝は不老不死の仙薬を求めるため「徐福」を東海の蓬来島へ遣わした、
この島は日本の事で徐福は土佐の虚空蔵山に登り霊薬を尋ねたとか、
紀州の熊野へ行ってそこで死んだというが何れも当てにはならん、徐福もわしの国へ来ておるが二千年も前のことは忘れたと言っておる。
秀吉も不老長寿をいたく希ったが、彼は却ってこれが禍をなし朝鮮の「沈維敬」に殺された、
そんな事を言ったら汝は疑うかも知れぬが、秀吉が朝鮮征伐の時朝鮮から「沈維敬」が使に来た、
秀吉と会見の際袂から飴玉の様なものを出してシャブッているので秀吉が不興に思い訊ねたところ、これは不老長寿の妙薬で八十四歳になつた私が遥々日本まで使に来れたのはこの妙薬の御陰で御座います
と答えたところ秀吉の不興はがらりと変り侍医の真瀬道三に聞くと
そんなこともあります、殿下もこの妙薬を貰って朝夕嘗めればよいと思いますと言上した。
秀吉はこの飴玉を貰ってなめているうち不明の病気にかかり死んだものじゃ、秀吉に贈った飴玉には小量の「亜比酸」を混入してあったので沈維敬にまんまと殺されたものじゃ、
沈椎敬が赤い舌を出してわしに言つたので 間違いないぞ」
こう言い終るとこの怪物は忽ち消え失せ、
杉の枝へ紙とも布とも判らぬものに書かれた秘法の一巻がぶら下げてあつた、
道順は三度いただきこれを持参して帰宅したが、
それ以来彼の名は益々高くその霊法は遂に天聴に達したという。
(土佐奇談実話集より・昭和三十二年)
少しでも読みやすくと思い改行を追加しています
改行以外は何も手を加えていません
感想
登山道
長岡郡本山町から大橋を渡り、野中兼山ゆかりの地、帰全山を経て北へ十四㌔、約三時間で頂上に達する。
標高一四七〇㍍、国境尾根の一支峰である。
この時は、まだ林道も通ってなかったんでしょうね
行川林道が復旧すれば本当に気軽に行ける山なんですが、、、
八反奈路にもあっと言う間に行けたんですが、、、
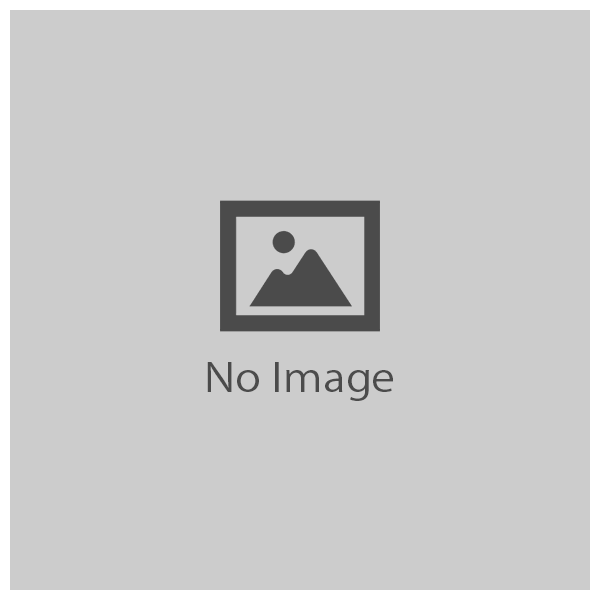
林道の一部通行止めのお知らせ(白髪山)|本山町
現在、道路工事のため以下の登山口へ続く林道が通行止めとなっております。
※2022年9月現在
この林道が復旧すれば本当に気軽に行ける山です
本山町のHPで工事中とありますが、、、
本当に工事進んでいるのかな???
ちなみに、、、
この林道、奥白髪の整備、個人が私財でやったそう
とんでもない金持ちですよねぇ。。。
この私財でやったって話し、、、どこで見たのか忘れましたが、、、
林道が途中で終わっている、林道を通しても意味があるとは思えない、八反奈路はどこも管理てない筈なんですが遊歩道を整備していた跡が今でもあり個人でやったと状況からも解ります
ヒノキ/八反奈路
昔からこの山はヒノキのほか、モミ、ツガの良材を産することで知られており、とくにヒノキは土佐名物の一つとして、長曽我部元親から豊臣秀吉へ献上されたという記録もある。
とにかくヒノキが凄いです!!
奥白髪の魅力は八反奈路に集約されています
個人的に山頂なんぞどうでもいいです
これは行川登山口からの登山道脇にある根下がりヒノキ
今は行くのに苦労しますよ。。。
ヒノキ四天王
今はモンベルがツアーを始めたのでロープが張られています
樹齢何百年のヒノキが信じられないほど沢山
今も元気に生きてます
奥白髪に限らず嶺北地域の山々は苔むした雰囲気の良い山ばかりです
八反奈路は赤丸の辺り一帯の事を言います
ルート見ると当時も歩いていますが
まだ整備されていなくて八反奈路と言う呼び名もなかったのでしょう
奥白髪に行くなら八反奈路は是非行って貰いたい
とにかく素晴らしい場所です
ただ、、、最近のアウトドアブームで人が増えるとマナーの悪い馬鹿も増える。。。
良い話聞きません。。。
某所の某大木も、、、馬鹿が訪れる機会が多くなって。。。
八反奈路は嶺北だけでも高知だけでもなく四国の財産、お宝です
大事に残して行きましょう
磁石が狂う?
「この山は、磁鉄鉱があって磁石が狂う。一度迷いこむと、二度と出られない」
奥白髪の中でもどこら辺なんだろう。。。
奥白髪に始めて行った時

奥白髪山のヒノキ四天王に会いにいったんですが、、、 | Trekking from Kochi
奥白髪のヒノキ四天王に会いにいったんですが、、、
デジカメ忘れるわガラケー落とすはで最悪でした。。。
この時はアプリを使っておらず八反奈路へ行く時に
と、一応コンパスセットしてから八反奈路を散策したんですがコンパスが狂う事は無かったです
少なくても分岐からヒノキ四天王の間はコンパスが狂う事はないです
バスを急がす?
五分間の停車時間に、煙草を吹かしていると、だしぬけに社長が現れたので仰天。
後発のバスの運転手を急がして、追いついたという。
いやいやいやいや凄い時代だ(笑)
七戸
九時五十五分、瓜生野(三七〇㍍)着。雑貨屋で、パン、味噌等を買い、登山コースを聞く。
地図に記載されているコースは、廃道となっているとのことで、詳しく教えてもらう。
このルート(七戸から)
現在も基本的には廃道ですが行ってる方もいます
ただ、、、
私有地があるので知らずに行くと、、、
トラブルになった話を聞きます
『七戸からは行かない方がいい!!』って方もいます
八反奈路へ行くには、現在ココが一番近いのですがお勧めはしません
トラブルあって嫌な気分になってもね。。。
この理由があるからモンベルもココからのツアーを行ってないんじゃないかな
七戸から行く方は慎重に。。。
風穴
十五時二十五分、風穴に行きあう。
穴には棚のような台があり(蚕種貯蔵の目的?)、宿泊もできるようになっているようだ。
これ、行川からの登山道にあるので現在は遠いです。。。
※2025年7月現在、モンベルのお陰か新しい行川登山口ができています
写真撮ってたと思ったんですが、、、
どこにもない。。。
立派な石垣もあります
確か、、、
この石垣の所、、、
いや、近くだったかな、、、
う~ん、、、
ハッキリ覚えてない。。。
白髪山の怪物
(土佐奇談実話集より・昭和三十二年)
どこまで実話かわかりませんが
昔、本山には凄いお医者さんがいたんでしょう
ググってみると、土佐奇談実話集を13,000円で売ってる古本屋さんがありました
読んでは見たいけど高い(^^;
山に遊びに行く時に
こんな話があったんだ、、、って思いつつ登るだけでも一味違いますよね
白髪山
もうひとつの白髪山です
こちらを白髪
記事の白髪山を通称奥白髪
と呼んでます

白髪山~初めての大型ザック | Trekking from Kochi
初めて20kgオーバーのザックを担いで山に行ってみました
現在の奥白髪山

奥白髪 | Trekking from Kochi
高知の奥白髪山紹介
行川からの奥白髪~八反奈路の記事です

滝山から八反奈路 | Trekking from Kochi
初めての滝山登山口から、ひっさびさに八反奈路に行ってきました
現在モンベルがツアーで使っている登山道
記事の意図
コピペで記事作成の意図はありません
目的は紹介、保存ですが
問題があればコメント、またはお問合せから連絡ください
必要であれば記事削除致します




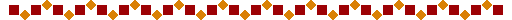
















コメントを投稿